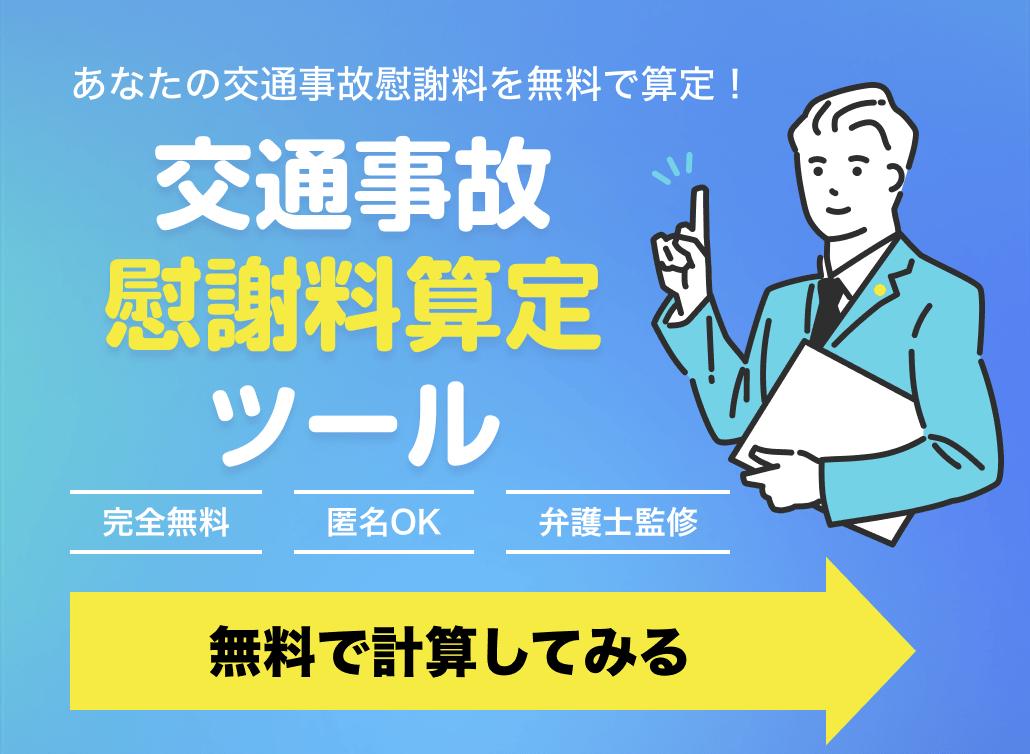後遺障害が認定されない理由とは? 対処法を解説
- 後遺障害
- 後遺障害
- 認定されない理由

交通事故でケガをして治療を続けたにもかかわらず、完全に治らずに症状が残ってしまうことがあります。このような場合、後遺障害の等級認定を受けることで、適切な損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、後遺障害が実際に生じていても、必ずしも認定されるとは限りません。書類の不備、検査不足、通院状況の問題などが原因で、認定を受けられないケースが多く見られます。後遺障害が認定されないと、本来受け取れるはずの慰謝料や逸失利益を請求できず、賠償額が大幅に減ってしまうおそれがあります。
交通事故による後遺障害の中でも多いのが、むち打ち損傷です。むち打ち損傷とは、追突事故などの際に首が鞭のようにしなることで、首や肩周辺の筋肉、靭帯、神経などが損傷される症状です。これらの症状は外見からは判断しにくく、客観的な証明が困難なため、認定のハードルが高いという特徴があります。
今回は、むち打ち損傷の後遺障害を中心に、後遺障害が認定されない主な理由や、認定されない場合の影響、そして有効な対処法について、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、後遺障害が認定されない理由とは?
交通事故でケガをして症状が残ったにもかかわらず、後遺障害が認定されずに、疑問や不満を抱く方は少なくありません。後遺障害等級の認定には厳格な基準があり、一定の書類や証拠がそろっていなければ、認定されないことも多いのが実情です。
以下では、後遺障害が認定されない主な理由と、認定されるために押さえておくべき要素について解説します。
-
(1)後遺障害が認定されない主な4つの理由
後遺障害が認定されない理由について、代表的な例を挙げると以下のとおりです。
① 後遺障害認定に必要な書類について、不備や不足がある
後遺障害認定は、基本的に書類審査によって行われます。そのため、必要な書類に不備や不足があると、後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
審査される書類のなかでも、特に医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が重視されます。しかし、後遺障害診断書の記載内容が曖昧であったり、必要な記載に漏れがあったりすると、等級認定が見送られてしまうことがあります。
そのため、後遺障害申請をする際には、記載内容の不備や記入漏れがないか、申請前によく確認することが重要です。
② 後遺障害を証明する他覚的所見や検査が不足している
後遺障害認定では、具体的な症状に応じてMRIやCT、X線などの画像検査、神経学的検査、可動域制限の測定などの検査が必要になります。症状が医学的に証明できる状態であれば、認定を受けられる可能性があります。
一方、ケガをした部位が「痛い」「動かしづらい」などと訴えても、それを裏付ける客観的な資料がなければ、後遺障害としては認められるのは難しいでしょう。
特にむち打ち損傷の場合、自覚症状のみでの後遺障害認定は非常に困難と言わざるを得ません。
③ 通院期間や通院日数が不足している
事故後の通院状況も、後遺障害の認定に大きく影響します。
通院の期間が短すぎたり、極端に間隔が空いていたりすると、「本当に治療が必要だったのか」「症状が継続していたのか」などと疑われ、後遺障害の認定を受けられなくなるおそれがあります。
症状によって異なりますが、むち打ち損傷の場合は、少なくとも6か月程度の継続的な通院が必要とされるのが一般的です。症状が改善したように感じても、通院を自己判断で中断することは避けましょう。
④ 後遺障害に連続性・一貫性が欠けている
事故発生から症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態)に至るまでの間、症状の経過が一貫していない場合も、後遺障害認定が難しくなります。
たとえば、事故直後には病院に行かず、数週間後に急に症状を訴え病院を受診したことが記載されていたり、痛む箇所が途中から変わったなどと記載されていたりする場合は、症状の連続性・一貫性がないとして、後遺障害認定されなくなる可能性が高まるでしょう。 -
(2)後遺障害が認定されるために必要な要素
後遺障害が認定されるためには、以下のような要素が存在することが重要です。
- 症状の連続性、一貫性:事故直後から症状固定まで、症状が変わらず継続している
- 通院記録の整合性:定期的な通院履歴があり、十分な通院期間がある
- 主治医の協力:後遺障害診断書を適切に記載してくれる医師がいる
- 検査結果の整備:MRI、神経学的検査、可動域測定などの客観的資料がそろっている
どのように対応すればよいかわからないときは、早めに弁護士に相談しましょう。
- 症状の連続性、一貫性:事故直後から症状固定まで、症状が変わらず継続している
2、後遺障害が認定されないとどのような影響がある?
後遺障害認定を受けられなかった場合、被害者には大きな不利益が生じます。以下では、後遺障害が認定されないことで生じる3つの影響について説明します。
-
(1)適切な後遺障害慰謝料を請求できない
後遺障害が認定されない場合、後遺障害慰謝料を請求することができません。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによる精神的苦痛への賠償金です。後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が定められており、症状が比較的軽く、もっとも低い後遺障害等級14級であっても110万円(自賠責基準だと32万円)が支払われます。
後遺障害が認定されないと、痛みなどに苦しんでいても後遺障害慰謝料は一切受け取ることができません。 -
(2)逸失利益を請求できない
後遺障害が認定されない場合、逸失利益を請求することができません。
逸失利益とは、後遺障害によって将来得られるはずの収入の一部を失うことに対する賠償金です。逸失利益は、後遺障害による労働能力の制限の程度によって金額が算定されるため、若年層で重い等級(数字の小さい等級)が認定された場合、逸失利益の金額は数千万円にまで及ぶケースもあります。
逸失利益は、将来の収入減少を補償するものです。そのため、後遺障害が認定されないと、将来の生活設計にも重大な影響を及ぼすおそれがあります。 -
(3)示談交渉が難航する可能性がある
後遺障害の等級認定は、示談交渉において賠償額を決める重要な役割を果たします。
後遺障害等級が認定されていれば、その内容をもとに慰謝料や逸失利益の金額が提示されます。一方、認定されていない場合は、保険会社側から後遺障害がないことを前提とした金額しか提示されません。
後遺障害等級が認定されないと、保険会社との示談交渉で後遺障害慰謝料や逸失利益を認めさせるのは困難になります。仮に裁判となった場合でも、後遺障害を立証するのは容易ではありません。
お問い合わせください。
3、後遺障害が認定されない場合の対処法とは?
後遺障害が認定されず、認定結果に納得できないときは、異議申し立てを行うことが可能です。異議申し立てを行うことで、場合によっては等級が認められるケースもあります。
ここでは、後遺障害が認定されなかったときの主な対処法について解説します。
-
(1)異議申し立てを行う
後遺障害が認定されないときのもっとも基本的な対応が、異議申し立てです。
これは、損害保険料率算出機構に対して再度審査を求める手続きであり、新たな証拠や検査結果等を追加して、前回の判断を覆すことを目的としています。
特に、次のようなケースでは、異議申し立てによって結果が変わる可能性があります。- MRIなどの画像所見を新たに提出できる
- 神経学的検査を受け直し、結果を明確にできた
- 医師の診断書の記載が不十分だったため、修正してもらった
異議申し立ては1回限りではなく、必要があれば複数回行うことも可能です。ただし、新たな証拠や資料を提出できなければ、何度申し立てをしても結論が変わることはありません。
-
(2)紛争処理制度を利用する
異議申し立てをしても結論を覆すことができなかった場合には、「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理制度を利用する方法があります。
これは、公平中立な第三者機関によって、自賠責保険会社・共済組合の結論の妥当性判断してもらう制度で、申し立ては無料で行うことができます。
紛争処理制度は、異議申し立てよりも専門的な観点からの判断に期待できますが、一度きりしか申請することができない点に注意が必要です。 -
(3)後遺障害認定に詳しい弁護士に相談する
後遺障害が認定されない場合は、後遺障害認定に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
後遺障害認定に詳しい弁護士に相談すれば、診断書の内容を精査し、医学的根拠を補強した異議申し立てが可能になります。
被害者自身では難しい異議申し立てや紛争処理制度の手続きも、弁護士が代行することで、負担を軽減しながら適切な後遺障害等級の認定が受けられることに期待できます。
後遺障害認定の結果に異議を申し立てるには、法的知識と医学的知識の両方が欠かせません。自分で対応が難しいときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
4、後遺障害認定を弁護士に相談すべき理由とは?
適正な後遺障害認定を受けるためには、後遺障害認定に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。以下では、後遺障害認定を弁護士に相談すべき理由を紹介します。
-
(1)後遺障害認定の裏付けとなる証拠や資料を集めてくれる
後遺障害認定を受けるには、診断書や検査結果、診療記録など症状の裏付けとなる医学的な根拠が不可欠です。しかし、知識や経験に乏しい方では、どのような資料が必要になるかわからず、申請時に重要な資料が漏れてしまうおそれもあるでしょう。
後遺障害認定に詳しい弁護士であれば、症状に応じた検査や後遺障害診断書の記載のポイントを熟知しています。そのため、認定に向けた適切な資料を収集して、後遺障害申請を行うことができます。 -
(2)被害者請求により適正な後遺障害認定の可能性を高めてくれる
後遺障害の申請手続きには、事前認定と被害者請求の2種類があります。
事前認定とは、保険会社が主体となって手続きを進める方法で、被害者は手間をかけずに対応できます。しかし、保険会社は認定の有利となる証拠や書類を積極的に集めてはくれません。
被害者請求とは、被害者が主体となって手続きを進める方法です。有利な資料を準備して請求できるため適正な認定を受けやすいです。
後遺障害認定の可能性を高める被害者請求の方が一般的に有利ですが、必要書類の収集や医師との調整など手続きが複雑で専門知識も必要になります。弁護士に依頼することで被害者請求の煩雑な手続きを任せながら、後遺障害認定の可能性を高めることができます。 -
(3)適切な不服申し立てを行ってもらえる
先述のとおり、後遺障害認定を受けられなければ、異議申し立てをすることで結論が覆る可能性があります。しかし、それには新たな医学的根拠の提出が欠かせません。
後遺障害認定に詳しい弁護士に相談すれば、認定を受けられなかった原因を精査し、それを補うための資料収集や説得的な異議申立書を作成するなどのサポートが可能です。
見落としがちなポイントを法的な視点で補足できるのは、大きなメリットといえるでしょう。 -
(4)弁護士基準で示談交渉をしてもらえる
後遺障害等級が認定されたら、保険会社と最終的な損害賠償額を巡る示談交渉を行います。
この際、弁護士が代理人として交渉を行うと、「弁護士基準(裁判基準)」に基づき、保険会社が提示した慰謝料を大幅に引き上げられる可能性があります。
たとえば、後遺障害等級14級が認定された場合、自賠責基準では慰謝料が32万円ですが、弁護士基準では110万円が基準になるため、受け取れる金額に3倍以上もの差が生じます。
少しでも賠償額を増やすには、弁護士によるサポートが不可欠です。示談交渉が始まる前に、弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
後遺障害の等級が認定されるかどうかは、交通事故後の損害賠償において非常に大きな意味を持ちます。しかし、後遺障害があっても、書類の不備や医療記録の不整合などによって認定を受けられなくなってしまうケースは少なくありません。
適正な後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害認定に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。まずはベリーベスト法律事務所 成田オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|