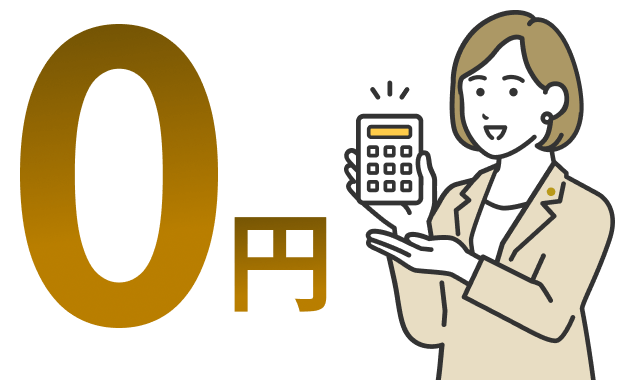遺産分割で不動産を分ける方法|手続きの流れや注意点を弁護士が解説
- 遺産分割
- 遺産分割
- 不動産

遺産分割協議を行う際に、揉め事になりやすいことのひとつが不動産の分割方法です。
不動産の分け方は複数あり、どの方法が適しているかは状況によって異なります。また、不動産の価値をどのように評価するかについても、専門的な検討が必要になります。弁護士のサポートでスムーズな不動産の遺産分割が期待できるでしょう。
本記事では、不動産の遺産分割についてベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、遺産分割で不動産を分ける4つの方法
遺産分割協議では、相続人の間でさまざまな遺産の分け方を話し合います。
不動産の分け方は複数あるため、相続人間で異なる意見が対立しがちです。「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法について、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
-
(1)現物分割
「現物分割」は、不動産を物理的に分ける方法です。
1個の建物を物理的に分けることが通常はできないので、基本的に現物分割は土地について選択肢のひとつとなります。登記簿上は一筆の土地でも、分筆すれば物理的に分けることができます。現物分割に向いているケース
複数の相続人が土地の取得を希望している場合ただし、土地の形状によっては公平に分けるのが難しいケースもあります。また、分筆の結果として面積が小さくなると、土地の使い勝手が悪くなることもあるので注意が必要です。
-
(2)代償分割
「代償分割」は、一部の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(=代償金)を支払ったり、金銭以外の財産を取得させたりする方法です。
代償分割に向いているケース
一部の相続人だけが不動産の取得を希望している場合
※土地は、代償分割と現物分割を組み合わせることも可能
例:AとBが土地を取得して現物分割を行い、Cに代償金を支払う
ただし、代償金や代わりの財産が準備できない場合は、代償分割を行うことは難しいでしょう。
また、代償金額の計算に当たっては、不動産を評価する必要があります。評価方法を巡って相続人間の対立が生じるケースがあるほか、不動産鑑定を行う場合は費用がかかる点にご注意ください。 -
(3)換価分割
「換価分割」は、不動産を売却して得た代金を分ける方法です。
換価分割は、以下のようなケースで有力な選択肢となります。換価分割に向いているケース
- 不動産の取得を希望する相続人がいない場合
- 不動産が遠方にあり、管理が難しい場合
- 現物分割や代償分割の話し合いがまとまらず、妥協案として不動産を売却する場合
- 相続税の納税資金を確保するため、不動産の売却が必要な場合
換価分割なら、1円単位で公平に売却代金を分けられます。また、不動産を管理する必要がなくなる点もメリットのひとつです。
ただし、売却によって不動産を手放すことになるので、思い入れのある土地や建物については、本当に換価分割をすべきかどうかよく検討しましょう。 -
(4)共有分割
「共有分割」は、不動産を複数の相続人で共有する方法です。
不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、その不動産は相続人全員の共同相続状態となります(民法第898条)。
共有分割は、以下の2通りに分けられます。① 法定相続分どおりに共有状態とするケース
② 協議により共有者や持分割合を調整するケース共有分割を選ぶケース
現物分割や代償分割の話し合いがまとまらない場合、いったん共有の状態で相続手続きを進めるという意味で、共有分割が選ばれることがあります
ただし後述するように、共有分割はトラブルの原因になり得るのでおすすめできません。迷ったら弁護士に相談するなどして、早期に、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかを選択することが望ましいでしょう。
2、遺産分割で不動産を分ける手続きの流れ
遺産分割に当たって不動産を分ける手続きの流れは、以下のとおりです。
-
(1)遺言書の有無と内容を確認する
まずは遺言書がないかを確認しましょう。遺言書があれば、原則としてその内容のとおりに不動産などの遺産を分けます。
遺言書は、亡くなった家族の遺品として保管されていることもある一方で、法務局や公証役場に保管されていることもあります。遺品に見当たらない場合は、最寄りの法務局や公証役場に照会してみましょう。
なお、法務局または公証役場で保管されているものを除き、遺言書を見つけたときは家庭裁判所の検認を受ける必要があります。 -
(2)法定相続人と相続財産を調査・確認する
遺言書によって分割方法が指定されていない不動産は、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)を通じて分け方を決めます。
なお、遺産分割協議の前には、法定相続人と相続財産を確定しなければなりません。法定相続人は、戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
相続財産は、家族が亡くなった時点で所有していた財産(+債務)です。不動産のほか、預貯金や現金、株式などをすべて調べてリストアップしましょう。困難な場合は、相続問題の実績がある弁護士に依頼することも可能です。 -
(3)遺産分割協議を行う|代償分割なら不動産の評価も必要
法定相続人と相続財産が確定したら、法定相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、不動産を含むすべての相続財産について、相続人間でどのように分けるかを話し合います。
合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、相続登記などを申請する際の必要書類となります。印鑑登録された実印での押印が必要です。
なお、代償分割を行う際には、他の相続人が取得する代償金などの適正額を知るため、不動産を評価する必要があります。不動産の評価方法としては、鑑定評価や不動産業者の査定、相続税評価額、固定資産税評価額を用いる方法などが挙げられます。
評価方法を巡って相続人同士で対立するケースもあるので注意が必要です。よく話し合い、できる限り全員が納得できる方法を選択しましょう。 -
(4)協議がまとまらないときは、調停・審判で分割方法を決める
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。調停委員の仲介の下で、各相続人の主張をすり合わせながら合意形成を目指します。
遺産分割調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判によって遺産分割の内容が決定されます。話し合いがまとまらない、法的な手続きが必要となった際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 -
(5)相続登記を申請する
遺産分割協議・調停・審判で決まった分割方法に従い、法務局に不動産の相続登記を申請しましょう。
相続登記は、不動産の名義変更手続きです。不動産の売却や賃貸を行う際には、それに先立って相続登記を経る必要があります。また、2024年4月1日以降は、相続によって不動産を取得した日または遺産分割の成立日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
遺産分割が完了したら、速やかに不動産の相続登記を申請しましょう。
お問い合わせください。
3、遺産分割で不動産を分ける際の注意点
遺産分割によって不動産を分ける際には、特に以下のポイントに注意しましょう。
-
(1)遺産分割協議書に分割の内容を明記する
相続人間の話し合いで決まった遺産分割の内容は、必ず遺産分割協議書に明記しましょう。
具体的には、以下のような事項を明記し、疑義のない内容とする必要があります。共通
- 被相続人を特定する情報
- 不動産の表示(登記事項証明書の内容を転記する)
現物分割の場合
- 土地を取得する相続人
- 分筆の方法(境界線、面積など)
代償分割の場合
- 不動産を取得する相続人
- 代償金または代替財産を取得する相続人
- 代償金の額または代替財産の種類、内容
換価分割の場合
- 換価(売却)の方法
- 売却代金を取得する相続人
- 売却代金の取得割合
-
(2)共有分割の場合、売却や賃貸の際には共有者間の意思決定が必要
共有不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要です(民法第251条第1項)。
また、共有不動産を賃貸に出す際にも、共有持分割合の過半数を有する共有者の同意が必要になります(民法第252条第1項)。
共有者間で意見が食い違っている場合には「共有物分割請求」を行うことができますが(民法第256条第1項)、訴訟に発展するケースも珍しくありません。
共有分割は、共有者である相続人間のトラブルに繋がるリスクがあるので、別の方法(現物分割・代償分割・換価分割)を選択することをおすすめします。 -
(3)債務超過の場合は、相続放棄も検討すべき
亡くなった家族が債務超過(=財産よりも、借金などの債務の方が多い状態)であった場合には、相続放棄を検討しましょう。
相続人は、亡くなった家族の債務も引き継ぐのが原則です。しかし相続放棄をすれば、債務の相続を回避することができます。
相続放棄の期間は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です(民法第915条第1項)。3か月が過ぎると、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
必要に応じて弁護士のサポートを受けながら、相続放棄の検討と準備を進めることをおすすめします。
4、相続トラブルについて弁護士に相談するメリット
不動産の分け方について相続人間で揉めてしまうなど、相続トラブルが発生した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
相続トラブルについて弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 家庭の状況に合わせた適切な遺産分割の方法についてアドバイスを受けられる
- 感情的に対立している相続人の間に入ってもらうことで、冷静な話し合いができる
- 相続人や相続財産の調査など、必要な手続きを任せられる
相続トラブルにお悩みの方は、深刻化する前に早い段階で弁護士へご相談ください。
5、まとめ
遺産分割で不動産を分ける方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つです。各相続人の希望を踏まえて、できる限り全員が納得できる分割方法を模索しましょう。
相続人間の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てる必要があります。調停の申立てに当たっては、相続問題の解決実績が豊富な弁護士のサポートを受けることが重要です。
ベリーベスト法律事務所は、遺産分割に関するご相談を随時受け付けております。不動産の分割についても、法的な観点から実情を踏まえて最適な方法をアドバイスいたします。
遺産分割トラブルにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|