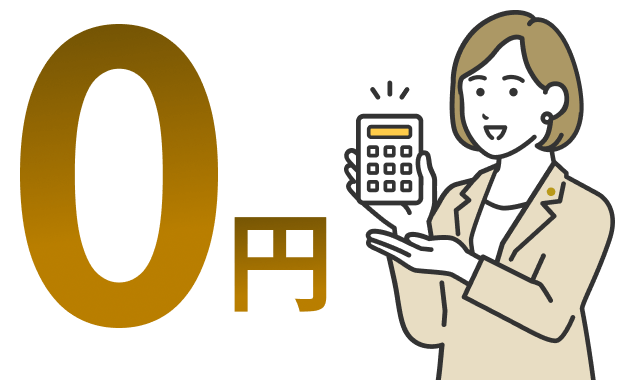遺言書は代筆で問題ない? 効力や公正証書遺言、注意点について解説
- 遺言
- 遺言
- 代筆

成田市統計書の公表によると、令和4年の千葉県成田市で亡くなった方の数は1281名でした。
相続において遺言書は重要な役割を果たしますが、代表的な遺言書に、自筆証書遺言があります。これは本人が自書する必要があり、原則として代筆は認められていません。
本記事では、自筆証書遺言の代筆の特徴、例外的に認められるケース、遺言書を自書することが難しい場合の対処法などを、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、自筆証書遺言は代筆できるのか?
自筆証書遺言の代筆は、財産目録を除いて認められません。代筆した自筆証書遺言は無効となります。
-
(1)自筆証書遺言とは
「自筆証書遺言」とは、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です(民法第968条)。
遺言書は、民法に定める方式に従って作成しなければなりません(民法第960条)。自筆証書遺言のほかには「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などが認められています。
自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書の方式です。他人が関与することなく、本人だけで作成できるため、自筆証書遺言は広く活用されています。 -
(2)代筆した自筆証書遺言は無効
自筆証書遺言は、必ず本人が全文・日付・氏名を自書しなければなりません。本人以外の者が全文・日付・氏名のうち一部でも代筆した場合、自筆証書遺言は無効になってしまいます。
完全に他人が代筆した場合のほか、他人が添え手などの補助をした場合も、自筆証書遺言は原則として無効となる点に注意が必要です。 -
(3)財産目録については、例外的に代筆も認められる
ただし、自筆証書遺言と一体のものとして、相続財産の全部または一部の目録(=財産目録)を添付する場合には、その目録については自書することを要しません(民法第968条第2項)。
上記は主にPCなどによる作成を想定した規定ですが、同規定に従い、財産目録については例外的に代筆も認められます。
ただし、財産目録を代筆によって作成する場合でも、遺言者本人がその目録の毎葉(=すべてのページ)に署名し、押印する必要があります。
2、自筆証書遺言の代筆が判明したらどうなる?
自筆証書遺言の代筆が判明すると、遺言は無効になります。
また、相続人が遺言書を偽造した場合は相続権を失うほか、偽造者は有印私文書偽造罪によって処罰されるおそれもあるのでご注意ください。
-
(1)遺言は無効|遺産分割が必要になる
民法で定められた方式に従っていない遺言書は、全体が無効となります。代筆によって作成された自筆証書遺言は全体が無効です。
この場合、自筆証書遺言に記載された遺産の配分は効力を有しないため、場合によっては、遺産全体について相続人全員で遺産分割を行う必要があります。
遺言者本人の意思を相続に反映できない上に、遺産の奪い合いが生じて相続トラブルに発展するおそれがあるので要注意です。 -
(2)遺言書の偽造に当たり、相続権を失うおそれがある
本人の意思に反して勝手に遺言書を代筆することは、遺言書の偽造に当たります。
相続人が遺言書を偽造した場合は欠格事由に該当し、相続権を失ってしまいます(民法第891条第5号)。遺産分割協議に参加できないだけでなく、遺留分の権利も失うことになります。 -
(3)有印私文書偽造罪によって処罰される
行使の目的で、他人の印章・署名を使用して権利・義務・事実証明に関する文書を偽造する等した場合は「有印私文書偽造罪」によって処罰されます(刑法第159条第1項)。有印私文書偽造罪の法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」です。
遺言書の偽造も、有印私文書偽造罪の構成要件に該当しますので十分ご注意ください。
3、遺言書の自書が難しい場合の対処法
遺言書を自書することが難しい場合は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成を検討しましょう。また、状況は限られますが、特別の方式による遺言が認められることもあります。
以下、自書が困難な場合の対策について詳しく解説します。
-
(1)公正証書遺言なら自書は不要
「公正証書遺言」は、公証人が作成する遺言書です。
遺言者から事前に聴取した内容に沿って、遺言者本人と証人2名の立ち会いの下で、公証人が公正証書遺言を作成します。法律の専門家である公証人が作成に関与するため、信頼性が高く、方式の不備で無効となるリスクがほとんどないのが公正証書遺言の特徴です。
公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言とは異なり、遺言者の自書は必要ありません。自書ができないほど健康状態が悪くても、遺言能力(後述)が認められれば公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則です。ただし、追加の費用を支払えば、自宅などへ公証人と証人に来てもらうこともできます。遺言者本人が公証役場へ行くのが難しい場合は、公証人に出張を依頼しましょう。 -
(2)特別の方式による遺言が認められることもある
遺言書は原則として、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式によって作成します。
しかし、これらの方式によることができない事情がある場合には、特別の方式による遺言が認められています。
本人が遺言書を自書できないケースでは、ごく限られた状況ではあるものの、以下の方式による遺言が認められることがあります。- 危急時遺言(民法第976条):疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立ち会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、遺言をすることができます。
- 伝染病隔離者の遺言(民法第977条):伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人および証人1人以上の立ち会いをもって遺言書を作ることができます。
- 在船者の遺言(民法第978条):船舶中に在るものは、船長または事務員1人および証人2人以上の立ち会いをもって遺言書を作ることができます。
- 船舶遭難者の遺言(民法第979条):遭難した船舶の中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立ち会いをもって口頭で遺言をすることができます。
なお、上記の特別の方式による場合であっても、筆記や署名・押印、家庭裁判所への確認請求など、効力を発生させるにあたり様々な方式や手続きが要求されます。
また、上記の特別の方式による遺言は、遺言者が普通の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)によって遺言をすることができるようになったときから6か月間生存するときは、その効力を生じません(民法第983条)。 - 危急時遺言(民法第976条):疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立ち会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、遺言をすることができます。
4、遺言書を作成する際の注意点
遺言書の内容に沿った相続を実現するためには、遺言書を作成するに当たって、以下の各点に注意しましょう。
-
(1)遺言能力の有無を事前に確認する
遺言書を作成できるのは、遺言能力を有する者に限られます。
遺言能力が認められるためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。- ① 15歳以上であること(民法第961条)
- ② 遺言の際に、遺言内容や遺言の法律効果を理解・判断するために必要な意思能力があること(民法第963条)
認知症などで判断能力が大幅に低下していると、意思能力が認められず、遺言が無効となってしまうおそれがあるので注意が必要です。
意思能力の有無は後に争われるケースもあるので、遺言書を作成する様子を録画するなどして、意思能力があったことを証明できるようにしておきましょう。 -
(2)遺言書を作成したことが分かるようにしておく
せっかく遺言書を作成しても、その遺言書が発見されずに終わってしまうケースがあります。そうすれば遺言がないものとして扱われてしまい、その効力は実質的に無に帰してしまうことになります。
したがって、遺言書の存在およびその保管場所は、生前において相続人に知らせておくのが望ましいですが、遺言の内容について反感を持つ相続人が改ざんしてしまったり、破棄してしまったりする危険もあります。
このような場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討することもひとつです。
参考:「自筆証書遺言書保管制度」(法務省) -
(3)紛失や改ざんを予防するには、公正証書遺言か保管制度の活用を
自筆証書遺言は、紛失したり、改ざんされたりするケースも少なくありません。
遺言書の紛失や改ざんを防ぐためには、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。遺言公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。
また自筆証書遺言についても、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書保管所で保管してもらうことで紛失や改ざんを防げます。
5、まとめ
自筆証書遺言は、本人以外の人が代筆することはできません。代筆された自筆証書遺言は、無効となってしまいます。
遺言書を自書することが難しい場合は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをおすすめします。弁護士にご相談いただければ、公正証書遺言の作成手続きのサポートはもちろん、円満な相続につながる遺言についてアドバイスいたします。
ベリーベスト法律事務所は、遺言書作成に関するご相談を随時受け付けております。遺言書を作成したいものの、自書することが難しく悩んでいる方は、まずはベリーベスト法律事務所 成田オフィスへご相談ください。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|