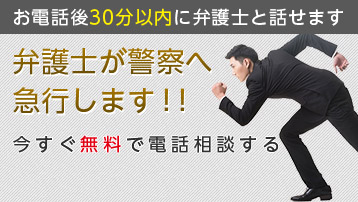うっかり他人の物を壊してしまった! 犯罪になる? 弁償はいくら必要?
- 財産事件
- 器物損壊
- 故意ではない
- 弁償

他人の家のガラス窓や壁、車などを傷つけたり、壊したりすると、器物損壊罪という罪に問われるおそれがあります。
では、うっかり他人の物を壊してしまった場合にも、罪になるのか、また弁償しなければならないのでしょうか。
今回は、故意ではないものの、他人の物を損壊してしまったときの法的な扱いと対処法について、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、器物損壊とは? 故意でなくても罪に問われるのか?
故意ではないものの、他人の物を壊してしまえば、罪に問われるのか気になる方もいるでしょう。以下では、他人の物を壊してしまった場合に問われることがある犯罪と、その概要について説明します。
-
(1)刑法における「器物損壊罪」とは?
器物損壊罪とは、他人の物を壊したり、傷つけたりした場合に成立する犯罪です(刑法261条)。器物損壊と聞くと、物理的に物を破壊する行為を連想されるかもしれませんが、「損壊」には、物を使用不能にする、価値を下げるなどの行為も含まれます。
具体的には、以下のような行為が器物損壊罪に該当します。- 他人の車に傷をつける
- 他人の家の窓ガラスを割る
- 店の看板を蹴って破壊する
- 他人の家のドアのカギ穴に接着剤を入れる
- 他人の食器に放尿する
器物損壊罪が成立した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。ただし、器物損壊罪は親告罪に該当するため、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。(刑法264条)
-
(2)過失による物の損壊は罪に問われない
日本の刑法では、過失(うっかり壊してしまった場合)による物の損壊を処罰する規定がありません。そのため故意ではない物の損壊は、刑事責任を問われません。
具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。- 不注意で他人のコップを落として割ってしまった
- キャッチボールの最中に誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった
- 駐車中、操作を誤って隣の車にぶつかってしまった
しかし、民事上の賠償責任が生じるため、被害者への弁償が必要になる場合があります。
2、民事上の損害賠償責任 弁償が必要なケース・免除されるケース
先述のとおり、過失によって物を損壊した場合には、民事上の損害賠償義務が生じるおそれがあります。民法709条では、不法行為責任として故意または過失により他人に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うと定められており、これは刑事責任とは別の法的責任です。
損害賠償義務が生じると原則的には弁償する必要がありますが、弁償が必要なケース・免除されるケースに分けて説明します。
-
(1)弁償が必要なケース
不注意で他人の物を壊してしまうことは、日常生活でも起こりえるトラブルです。ただし、必ずしも弁償が必要になるとは限りません。物の損壊で弁償が必要になる具体的なケースを紹介します。
① 店舗での商品を壊した
店舗では、以下のように商品を壊してしまうケースがあるでしょう。- お店で商品を選んでいる際、手に取った商品をうっかり落としてしまう
- お店の通路を歩いている際、手に持っていたかばんが商品棚に当たって、棚にあった商品を落としてしまう
このような不注意による物の損壊があった場合には、民事上の賠償義務が生じます。そのため、お店に対して壊した商品の弁償をしなければなりません。
② 借家・賃貸住宅で壁や床を壊した
賃借人には、賃貸借契約に基づく原状回復義務があるため、賃借人が故意または過失により生じさせた損耗については、退去時に原状回復費用を負担しなければなりません。
賃借人が原状回復義務を負うとされるケースには、以下が挙げられます。- 飲み物をこぼしてできたシミ
- 家具をぶつけてできた壁の穴
- ペットによる床や壁の傷
- タバコのヤニ汚れやにおいの付着
ただし、通常の使用方法で生じた損耗や、経年劣化により生じた損耗については、原則として賃借人の原状回復義務の範囲外です。
③ 運転中に看板などにぶつけて壊した
車を運転している際に、不注意で壁や看板などにぶつかってしまうこともありえます。また、駐車場で操作を誤り、隣の車にぶつけてしまうこともあるでしょう。
このように、車の運転中に生じた物の損壊についても、被害者への弁償が必要です。もっとも、自動車保険に加入していれば、保険会社から被害者へ支払いがなされる場合が多く、加害者が直接対応するケースは少ないでしょう。 -
(2)弁償が免除されるケース
他人の物を壊してしまったとしても、以下のようなケースに該当する場合であれば、被害者への弁償が免除される可能性があります。
① 緊急避難
緊急避難とは、生命・身体・自由・財産を守るために、別の方法がなかった場合であれば、やむを得ず他人の物を壊したり、他人を傷つけたりしてしまっても法的責任に問われないという制度です。
たとえば、以下のような行為が緊急避難にあたり、法的責任を問われることはありません。- 地震が起きてお店に閉じ込められてしまったため、脱出するために窓ガラスを割った
- 火事が起きたため、隣人を救うために窓ガラスを割って家に立ち入った
ただし、危険を避けるための行為としてやりすぎてしまったときは、「過剰避難」として被害者への弁償が必要になることもあります。
② 正当防衛
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己や他人の身を守るためにやむを得ずした行為については法的責任を問われないという制度です。
たとえば、以下のような行為が正当防衛にあたります。- 相手が急に殴りかかってきたため、相手を押さえつけた際に相手の服が破れた
- 襲ってきた相手が持っていたスタンガンを地面にたたきつけて壊した
なお、正当防衛も、身を守るための手段として行き過ぎていたと評価されると「過剰防衛」にあたり、被害者への弁償が必要になることがあります。
③ 被害者が弁償を受ける意思がない
他人の物を壊してしまったときは、基本的には被害者への弁償が必要になります。
しかし、被害者が弁償(損害賠償請求権)を放棄している場合には、被害者への弁償は必要ありません。
たとえば、お店で物を壊してしまったとしても、安価なものだった場合には、お店の好意で弁償が免除されることもあります。
ただし、弁償を放棄するかどうかは被害者が決めるため、加害者側から放棄を強要することはできません。 -
(3)弁償が必要なときの金額
弁償が必要なときの金額は、壊してしまった物の価値を踏まえて決められます。
弁償額を決める際には、以下のような要素が考慮されます。
① 修理費用
壊れた物が修理可能であれば、その修理にかかる実費が弁償額の基本となります。修理期間中に代替品をレンタルする必要がある場合は、そのレンタル費用も含まれることがあります。
② 買い替え費用
修理が不可能な場合や修理費が高額になる場合は、買い替え費用で算定します。この場合の金額は、同等の中古品の市場価格、つまり新品価格から使用による減価分を差し引いた「時価額」が基準となります。
③ 使用不能による損害
壊された物が営業に使用されていた場合は、修理や買い替えが完了するまでの期間中に生じる営業損失も賠償対象となることがあります。
④ 精神的苦痛への慰謝料
物を壊されたことによる精神的苦痛への慰謝料は、原則として認められません。しかし、壊された物が故人の形見や特別な記念品など、被害者にとって特別な意味を持つ物であった場合や、ペットが怪我をした場合、例外的に慰謝料が認められる場合があります。
これらの要素はあくまで考慮要素であり、弁償額に明確な計算式があるわけではありません。物の状態、被害者との関係性、壊した状況などによって弁償額は大きく変わります。
そのため当事者同士の話し合いでまとまらないときは弁護士に相談するとよいでしょう。
お問い合わせください。
3、警察沙汰になりそうな場合の対応は?
過失による物の損壊だとしても、被害者が「警察に行く」などと言っている場合には、以下のような対応が必要です。
-
(1)感情的にならず冷静に話をする
加害者は、被害者から感情的な言葉を受ける可能性が大いにあります。壊された物が被害者にとって大切な物であったなら、怒りの感情をぶつけられてしまうのも仕方ないといえるでしょう。
被害者から感情的な言葉を投げかけられたとしても、落ち着いて話をすることが大切です。激しい口論になると収拾がつかなくなってしまうため、加害者側は絶対に感情的にならないよう注意が必要です。 -
(2)損壊に至った事情を説明する
被害者の気持ちが落ち着いた際は、被害者の物を壊してしまった事情や経緯を丁寧に説明するようにしてください。
過失による損壊だったという事情が明らかになれば、被害者の怒りの感情も多少は和らぐ可能性があります。事情をわかってもらえれば、今後の示談交渉もスムーズに進みやすくなるため、時間をかけて説明をするべきでしょう。 -
(3)謝罪・弁償を申し出る
他人の物を壊してしまったのであれば、すぐに被害者に対して謝罪を行い、壊してしまった物の弁償を申し出るようにしてください。
弁償額については、被害者との話し合いによって決めていくことになりますが、当事者同士の話し合いが困難な場合は、弁護士に相談するのをお勧めします。
弁護士であれば、示談交渉だけではなく、後日「払ってもらっていない」などとトラブルにならないよう、法的に有効な示談書の作成などのサポートも行うことができます。
4、弁償や示談を進める際の注意点
被害者との弁償や示談を進める際には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)相手が感情的になっている場合の対応
相手が怒っていたり、興奮していたりするときは、冷静な話し合いができる状況を整えることが最優先です。
まずは、誠意をもって相手に謝罪をするとともに、相手の言い分に対しては反論せずに冷静に話を聞くようにしてください。その際には、相手の気持ちに寄り添うやりとりを心がけることで、相手にも誠意が伝わりやすくなるでしょう。
また、相手が感情的になっている場合、その場での示談交渉は避けるべきです。
相手が感情的な状態では、交渉をしようとしても話が進まないため、被害者の言い分を一通り聞いたのち、「後日改めて、弁償の話をする時間をとらせていただけませんか」などと丁寧に提案するとよいでしょう。 -
(2)現金受け渡し時の注意点
弁償金を現金で支払う際には、あとから「もらっていない」「金額が違う」といった主張をされることもあるかもしれません。トラブルを避けるためにも、証拠を残すことが大切です。
そのためには、示談書の作成が必要になります。法的に有効な示談書を作成しておけば、示談に関する将来のトラブルを予防することが可能です。
また、支払った証拠を残すためにも、現金の手渡しではなく、銀行振り込みを検討したほうがよいでしょう。 -
(3)金額交渉のトラブルを避けるために弁護士を交えることのメリット
示談交渉では、感情的な被害者を相手にすることになるため、法的知識や交渉経験のない方では、トラブルに発展するおそれもあります。このようなトラブルを回避するためにも、示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉をすべて任せられるため、感情的な対立を和らげながらスムーズに話し合いを進めることができます。
また、示談金の額についても、相場を踏まえて適正な金額で交渉をすすめることができ、法的に有効な示談書の作成もサポート可能です。
自分で対応することに少しでも不安がある方は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
他人の物をうっかり壊してしまった場合は、原則として器物損壊罪にはあたりませんが、民事上の責任を問われるおそれがあります。
相手との示談交渉が不安な場合や、相手とのやりとりに行き詰まってしまった場合は、弁護士によるサポートを検討しましょう。まずはベリーベスト法律事務所 成田オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています