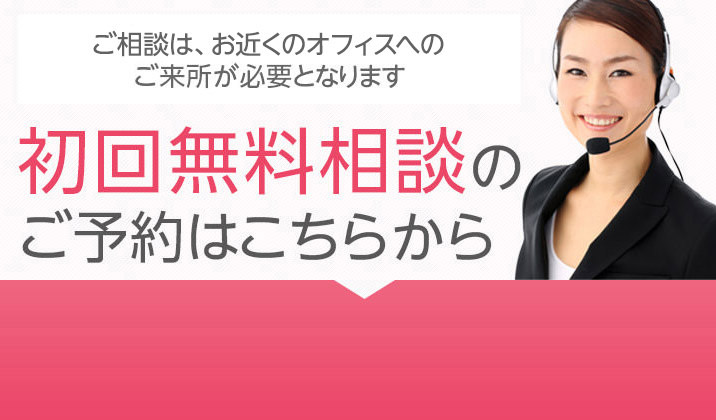片親疎外とは? 離婚や面会の際に別居親が取るべき行動と法的対応
- その他
- 片親疎外

片親疎外とは、子どもが片方の親の影響を受けて、もう片方の親との交流を拒絶する状態を指す言葉です。離婚する際に親権や面会交流で有利になろうとして、同居親が子どもに対して、別居親の悪口を吹き込むことがあります。こういった言動が原因で、片親疎外の状態が生じることがあるのです。
別居親としては、離婚後に子どもと交流することは子どもの成長を身近で感じることができる大切な機会です。そのため、片親疎外の状況は決して好ましい状況とはいえないでしょう。このような状況が生じたとき、別居親はどのような対応ができるのでしょうか。
今回は、片親疎外とは何か、片親疎外が起きたときにとるべき行動と法的な対応について、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの弁護士が解説します。


1、片親疎外とは何か?
片親疎外とは、具体的にどのような状態なのでしょうか。以下では、片親疎外の定義や原因、子どもに与える影響などについて説明します。
-
(1)片親疎外の定義
片親疎外とは、子どもが片方の親(主に同居親)の影響を受けて、正当な理由なく、もう片方の親(主に別居親)との交流を拒絶する状態を指す言葉です。片親疎外のことを「片親疎外症候群」と呼ぶこともあります。
同居しているときは何も問題なかった親子関係が、別居をきっかけに突然悪化し、子どもが別居親に対して嫌悪感などを持つことがあります。このような状況が生じたときは「片親疎外」を疑った方がよいでしょう。
なお、別居親によるDVなど、子どもが別居親を拒絶するに至った直接的な原因があるときは、片親疎外には該当しません。 -
(2)片親疎外が発生する主な原因
片親疎外が発生する主な原因としては、以下のようなことが考えられます。
片親疎外の主な原因
- 同居親が子どもの前で別居親のことを誹謗中傷したり、拒絶をする
- 子どもが別居親の話題を同居親に振ると嫌な顔をする
- 子どもに対して別居親の話題を出すことを禁止する
- 同居親が別居親との面会交流時に、あからさまに嫌な態度をとる
-
(3)片親疎外が子どもに与える影響
正当な理由もなく、片方の親によって意図的に子どもを引き離す行為は、子どもの福祉を害し、以下のようなさまざまな悪影響を与える可能性が懸念されます。
- 情緒不安定
- 対人関係の困難
- 抑うつ傾向
- 依存傾向
上記以外にもさまざまな問題を引き起こす可能性がありますので注意が必要です。
2、片親疎外が親権判断や面会交流に与える影響
片親疎外は、夫婦の離婚問題の中でも親権や面会交流に影響を与える可能性があります。
-
(1)裁判所が親権を判断する際への影響
離婚時に子どもの親権に争いがある場合には、最終的に裁判所が親権者の適格性を判断します。親権者の適格性を判断する要素には、さまざまなものがありますが、子どもに対する養育態度も重要な要素のひとつです。
片親疎外行為を行う親の養育態度は、子どもの健全な発達を阻害する要因として否定的に評価される可能性があります。よって、裁判所が親権者の適格性を判断する際には、同居親に不利な要素として考慮されます。
また、子どもの年齢が15歳以上だと親権者の判断の際に子どもの意見が必ず聴取されることになります(家事事件手続法152条2項、人事訴訟法32条4項)。15歳未満の子どもであっても10歳前後であれば一定の判断能力が備わっていますので、子どもの意思を尊重して親権者を決めるようになっています。
このように子どもの意見は、親権者の適格性判断にあたって重要な要素になりますので、「一緒に暮らしたくない」、「嫌い」などの意見が出てしまうと、別居親にとって不利な事情として考慮されてしまいます。そのため、片親疎外が原因である場合には、裁判所にその旨をしっかりと主張していかなければなりません。 -
(2)離婚後の面会交流への影響
面会交流とは、別居や離婚により子どもと離れて暮らしている親(=非監護親)が、子どもと定期的かつ継続的に直接の面会や手紙・電話のやり取りなどで交流することをいいます。面会交流は、子どもが健全に発達・育成していくために重要な制度ですので、子どもおよび非監護親の権利として認められています。
片親疎外が発生すると、当初は何の問題もなく面会交流が実施できていたにもかかわらず、突然子どもが「会いたくない」などと言いだし、面会交流の実施が困難になることがあります。また、面会を実施できたとしても、子どもの親に対する態度が悪化し、これまでのような円満な面会交流が難しくなることもあります。
非監護親にとって面会交流は、別居・離婚後に子どもと面会できる唯一の機会ですので、それを奪われることになるのは大きな苦痛といえるでしょう。
お問い合わせください。
3、別居親が取るべき具体的な対策
片親疎外が生じた場合、別居親としては、以下のような対策をとる必要があります。
-
(1)子どもとのコミュニケーションを維持する
片親疎外による弊害を回避するには、別居親としても子どもとのコミュニケーションを維持することが大切です。
別居親とのコミュニケーションが維持されていれば、子どもも別居親に対して悪い感情を持ちにくくなりますので、片親疎外を防止できる可能性があります。
別居・離婚により子どもと離れて暮らすことになると、以前よりもコミュニケーションの頻度が減ってしまいますが、面会交流の頻度や時間を増やすことで子どもとの良好な関係を維持することが期待できます。 -
(2)同居親との関係改善のためのアプローチをする
片親疎外は、同居親と別居親が不仲であることが原因で発生します。
同居親と別居親が円満な関係であれば、同居親から子どもに対して悪口や誹謗中傷が伝わることはないと考えられますので、片親疎外を防止できる可能性があります。
別居や離婚に至った原因によっては難しい面もありますが、同居親との関係改善のためにアプローチをすることも有効な手段といえるでしょう。 -
(3)第三者機関や専門家のサポートを受ける
同居親と別居親との関係性が悪いと、そのことが原因で面会交流が実施できないケースも少なくありません。面会交流が実施できない状態が続くと、同居親による影響によって片親疎外が生じるリスクが高くなりますので、別居親にとっては決して好ましい状況とはいえないでしょう。
同居親と別居親だけでは面会交流が難しいときは、自治体や民間の支援機関など、第三者機関のサポートを受けることも検討しましょう。面会交流の調整や立ち会いに第三者が関与することで、スムーズに面会交流を実現できる可能性があります。 -
(4)弁護士のサポートのもと法的手段をとる
片親疎外により親権の獲得や面会交流の実施に影響が生じているときは、自力で対応するのは困難です。このような状況を脱するには、専門家のサポートを得ることで解決できる可能性があります。
弁護士であれば、親権や面会交流権の獲得に向けて、法的な観点からのアドバイスが可能です。また、調停や裁判においても、相談者の主張を的確に伝えながら、手続きや交渉を行うことができます。
片親疎外が原因で、親権についての主張や面会交流の実施がうまくいかない場合は、弁護士に依頼して法的なサポートを受けることをおすすめします。
4、親権や面会交流でトラブルになった場合の手続き
親権や面会交流でトラブルになったときは、以下のような手続きによりトラブルの解決を図ることができます。
-
(1)証拠集め
片親疎外により親権や面会交流に影響が生じているときは、後述するような調停や審判により解決を図ることができます(調停や裁判については、「(2)親権や面会交流に関するトラブルを解決する流れ」で解説します)。
しかし、調停委員や裁判官に片親疎外が発生していることを伝えても、それを裏付ける証拠がなければ信じてもらうことは難しいです。そのため、親権や面会交流でトラブルが生じたときは、まずは片親疎外が発生していることの証拠を集めることが大切です。
片親疎外が発生している証拠としては、主に以下のようなものが考えられます。片親疎外が発生していることを裏付ける証拠
- 同居親が子どもに対して別居親の悪口を言っているところの録音、録画
- 同居親から送られてきた面会交流を拒否する内容のメールやLINE
- 面会したいのにさせてくれないという内容の子どもから送られてきたメールやLINE
なお、どのような証拠が必要になるかは具体的な状況によって異なりますので、弁護士に相談しながら証拠を収集しましょう。
- 同居親が子どもに対して別居親の悪口を言っているところの録音、録画
-
(2)親権や面会交流に関するトラブルを解決する流れ
親権や面会交流に関するトラブルが生じたときは、以下のような流れで解決を図ります。
① 当事者同士の話し合い
親権や面会交流に関するトラブルが生じたときは、まずは当事者同士の話し合いにより解決を図ります。トラブルの原因がどこにあるのかを見極めたうえで、相手との話し合いを行っていきましょう。
当事者同士の話し合いでは感情的になり、解決できそうにない場合には、相手との交渉を弁護士に任せるという方法もあります。
弁護士であれば、手紙や電話などを通じて、相手との交渉を行うことができます。
② 家庭裁判所の調停・審判
当事者同士の話し合いではトラブルが解決しないときは、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停は話し合いの手続きですが、調停委員が間に入って調整をしてくれますので、当事者だけの話し合いよりもスムーズな解決が期待できます。
親権者の変更や面会交流に関するトラブルに関しては、調停が不成立になれば自動的に審判に移行し、裁判所が一切の事情を考慮して判断することになります。 -
(3)別居親の主張が認められた審判例
以下では、面会交流に関して別居親の主張が認められた審判例を紹介します。
① 名古屋家裁平成28年8月31日審判
同居親が別居親による性的虐待を理由に面会交流を拒絶していた事案について、裁判所は、性的虐待等の存在を基礎づける具体的な根拠は認められないとして、別居親と子どもとの面会交流を認めました。
審判では、幼児や児童の供述については、記憶の正確性に不十分な点があること、大人に対する迎合性が強いこと、他者からの情報を自己の体験かのように思いこんでしまうことがあるため、慎重に検討する必要があるとしています。
② 大阪高裁令和元年11月8日決定
別居親が、同居親に対し、調停事件の調停条項に基づく面会交流が実施されなくなったとして、子どもとの面会交流を求めた事案について、裁判所は、間接交流のみを認めた原審判を変更し、従前の父子関係が良好であったこと、未成年者らの心情、直接交流時の状況等から直接交流を禁止すべき理由は見当たらず、直接交流を速やかに再開することが子どもの福祉にかなうとして、間接交流ではなく直接交流を認めました。
5、まとめ
別居や離婚をきっかけに親と子どもが別々に暮らすことになると、同居親からの影響により片親疎外が生じることがあります。
片親疎外は、子どもの健全な成長に悪影響を与える可能性がありますので、別居親としては、片親疎外にならないようにするためのコミュニケーションや弁護士など第三者も含めたサポートを受けることが重要です。
片親疎外により親権や面会交流に影響が生じているときは、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|